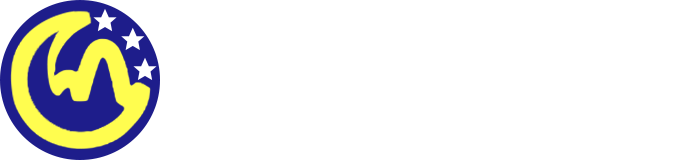- HOME>
- 変形性股関節症
変形性股関節症とは
股関節は、骨盤側の寛骨臼(かんこつきゅう)と、太ももの骨である大腿骨頭からなる球関節です。正常な状態では、関節軟骨によって滑らかな動きが保たれていますが、この軟骨が摩耗することで痛みや動きの制限が生じる状態を変形性股関節症と呼びます。
特に40〜50代の女性に多く見られ、全国で400〜500万人の患者がいると言われています。歩行時には体重の約10倍もの負荷が股関節にかかるため、症状が進行すると日常生活に大きな支障をきたす可能性があります。
変形性股関節症の原因
変形性股関節症の主な原因として
| 臼蓋形成不全 | 骨盤側のくぼみが浅く、大腿骨頭をしっかり覆えない状態で、全体の約8割を占めます。 |
|---|---|
| 加齢による変化 | 年齢とともに関節軟骨が摩耗することで発症します。特に女性は筋肉量が少ないため、発症リスクが高くなります。 |
| 生活習慣 | 肥満、過度なスポーツ活動、長時間の立ち仕事などが原因となることがあります。 |
こんな症状はありませんか?
- 歩き始めに太ももの付け根が痛む
- 長時間の歩行で股関節に違和感がある
- 靴下を履くときに痛みを感じる
- 足の爪切りが困難になってきた
- 階段の上り下りが辛い
- 正座がしづらくなった
- 寝返りで痛みがある
- ズボンやスカートの丈に左右差がある
変形性股関節症は進行する病気
変形性股関節症は次の段階を経て進行していく病気です。早期発見できた場合は、生活習慣の改善や予防的な運動療法により、症状の進行を遅らせることができます。
前股関節症
この段階では、まだ明確な痛みや症状は現れていませんが、股関節を詳しく検査すると、骨盤側のくぼみ(臼蓋)が浅いなど、軽度の形状異常が見られる状態です。レントゲン検査では関節の軟骨の変化などは見られませんが、このような形状異常があると、将来的に変形性股関節症に進行するリスクが高くなります。
初期
動き始めに痛みを感じますが、しばらく動くと和らぐことが特徴です。関節の隙間が狭くなり始め、約5年で90%の方が進行期へ移行します。
進行期
日常動作全般で痛みを感じるようになり、正座や階段の昇り降りが困難になります。関節の隙間が明確に狭くなり、骨に変形が見られます。
末期
安静時でも痛みを感じ、歩行が困難になります。足の長さに左右差が生じ、関節の可動域が著しく制限されます。
変形性股関節症の治療
保存療法について
症状の進行を抑制し、痛みを和らげるために、以下のような保存療法を行います。これらの治療法は、患者さんの状態や生活環境に合わせて適切に組み合わせて行います。定期的な通院により、症状の変化を確認しながら、治療内容を適宜調整していきます。早期から適切な治療を開始することで、症状の進行を抑制し、より良好な経過が期待できます
運動療法
股関節周囲の筋力維持・向上を目的とした運動を行います。特に体重による負担を軽減できる水中ウォーキングや水泳運動が効果的です。水中では週2-3回程度の運動が推奨されます。また、お尻周りの筋肉(中臀筋)のトレーニングや、股関節周囲のストレッチ運動も重要な運動療法の一つです。ただし、過度な運動は症状を悪化させる可能性があるため、専門家の指導のもと、痛みを誘発しない範囲で行うことが大切です。
薬物療法
痛みの程度に応じて、適切な薬物療法を行います。主に非ステロイド性抗炎症薬を使用し、内服薬、外用薬、座薬など、患者さんの状態に合わせて投与方法を選択します。特に痛みが強い場合は、より強い鎮痛剤の使用を検討することもあります。定期的な経過観察を行いながら、副作用にも十分な注意を払って治療を進めていきます。
物理療法
血行を促進し、痛みの緩和を図る物理療法も効果的です。温熱療法を中心に、局所の血流を改善し、症状の緩和を目指します。炎症が強い時期には、必要に応じてアイシングを行うこともあります。状態に応じて超音波治療や電気治療などを組み合わせることで、より効果的な治療が期待できます。
生活指導
日常生活での負担を軽減するための指導も重要な治療の一つです。適切な体重管理と食事指導を行うとともに、股関節に負担の少ない動作の指導を行います。必要に応じて杖の使用も検討します。また、和式から洋式への生活様式の変更や、長時間の同じ姿勢を避けること、重い物を持つ動作を制限するなど、具体的な生活上の注意点についても指導していきます。
手術療法
保存療法で改善が見られない場合、関節鏡視下手術や人工股関節置換術などを検討します。
早期発見・早期治療が重要な疾患ですので、気になる症状がございましたら、お気軽に当院にご相談ください。